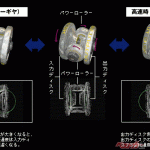常にイノベーションが生み出される自動車。革新的な新技術として登場し、現在はスタンダードになっているものも多いが、なかにはさまざまな理由で定着できずに終わってしまったテクノロジーもある。今回は、そうした悲劇のテクノロジーを振り返っていくことにしたい。いったい何がマズかったのか?
文/長谷川 敦、写真/マツダ、アウディ、日産、シトロエン、トヨタ、ポルシェ、FavCars.com、Newspress UK
【画像ギャラリー】あまりに革新的すぎた!? 姿を消してしまったテクノロジー(16枚)画像ギャラリー
マツダのみが実用化したロータリーエンジン。果たしてその未来は?
一時期はマツダの代名詞とも言える存在だったのがロータリーエンジンだ。ピストンの往復を回転運動に変換するレシプロエンジンとは違い、おむすび型のローターが回転して動力を生み出すロータリーエンジンは、マツダが世界で唯一完全実用化に成功し、数多くの市販車にも採用している。
ロータリーエンジン自体の歴史は古く、実用化に向けて数多くの試みがあったが、1950年代にドイツ人技術者のフェリクス・ヴァンケルが完成させ、1957年にはドイツの自動車メーカー・NSUによって試作品が誕生している。
NSUは1964年に世界初のロータリーエンジン搭載市販車のヴァンケル スパイダーを発売するものの、その完成度は低く、特にスパイダーに続いて販売されたRo 80ではトラブルが続出。販売成績も伸びずに、やがてNSUはアウディに吸収合併されることになる。
ロータリーエンジンのメリットは、エンジン全体をコンパクトにできることやそれによる軽量化、振動の少なさや排気量あたりのパワーが大きいことなどが挙げられる。しかし、実用化までの技術的ハードルは高く、NSUに続くメーカーも完全実用化を成し遂げることはできなかった。
そこで名乗りをあげたのが日本のマツダだった。独自の技術によって他メーカーとの差別化を狙ったマツダは、1961年の段階でNSU社とのロータリーエンジンに関するライセンス契約を締結して独自のロータリーエンジン開発に着手。さまざまな試行錯誤を重ねてついに量産と実用に耐えうるロータリーエンジンの開発に成功した。
マツダ初のロータリーエンジン搭載市販車のコスモスポーツは1967年に販売が開始され、日本はもとより世界中にセンセーションを巻き起こした。これによって「ロータリーのマツダ」を確立し、以降はRX-7シリーズなど、数多くのロータリーエンジン搭載車を世に送り出すことになる。
コンパクトかつ高出力のロータリーエンジンはスポーツカーに最適であり、実際にマツダの2&3代目RX-7は生産終了から20年近くが経過した現在でも高い人気を保っている。だが、そうしたマツダのロータリーエンジン搭載車の系統も2012年のRX-8販売終了をもって途絶えてしまっている。
ロータリーエンジンには利点が多い反面、燃費の悪さやオイル消費量の多さなど、エコが重視される現代では致命的とも言える難点がある。これは構造に起因するところが大きく、マツダの技術力を持ってしても、レシプロエンジンに対する燃費面の不利などを覆すことができなかったのだ。
こうして現在は市販のロータリーエンジン搭載車が存在していないが、実はロータリーエンジンには水素燃料との相性が良いなどの特徴もある。つまり、もしかするとロータリーが華麗なる復活を遂げる未来が待っているかもしれない。ロータリーエンジンのファンならば、その日が来ることを期待して待ちたい。
(編集部注/ロータリーエンジンは、純粋なスポーツエンジンとしてではなく、電動車のレンジエクステンダー用(発電用)として2023年頃の登場が期待されております)
エクスロイドCVTは繊細すぎたことで残念な結果に
自動車の速度はエンジンの回転数とギヤチェンジによって調整される。現在の日本でメジャーなのは自動的にギヤチェンジを行うオートマチックトランスミッションだ。こちらはトルクコンバ―タ―という機構を使うシステムだが、無段階変速が可能なCVT(Continuously Variable Transmission)方式を採用したクルマも多い。
“トルコン”式に比べてCVTでは変速時のショックがほぼなく、燃費が良いなどのメリットがあり、コストも抑えられるために軽自動車でも数多く用いられている。しかし、エンジンパワーが大きくなると効率が落ちるなどの問題もある。
こうした問題を解決するために生み出されたのがエクストロイドCVTだった。
1999年に日産が発売したセドリック&グロリアに採用されていたのがこのエクストロイドCVTで、従来のベルト式CVTとは異なり、ディスクとパワーローラーによって動力を伝達するのが特徴。
それまでのCVTの弱点だった大排気量&高出力にも対応し、素早いレスポンスと滑らかで力強い加速を実現。さらに従来のオートマ車に比べて約10%の燃費向上も達成していた。
ここまで見る限りでは理想的なトランスミッションに思えるエクストロイドCVTだが、現実はそううまくは運ばなかった。最初の問題は製造コストで、部品点数が多く複雑な構造になるエクストロイドCVTはどうしてもこの難点を解決できなかった。
また、複雑ゆえにその取り扱いもデリケートであり、高価な専用オイルが必要なこと、そして故障の際に部品交換ができず、トランスミッションを載せ換えなくてはならないことなど、問題点は多かった。
鳴り物入りで登場したエクストロイドCVTだったが、上記の問題は根が深く、結局2004年をもって生産を終了。予想外の短命に終わってしまった。
シトロエンの粘り腰もハイドロサスを残せず
伝統的な金属製スプリングではなく、液体とガスによって車体を支え、走行中のショックも吸収・減衰するのがハイドロニューマチック・サスペンションだ。スプリングに換えて空気を利用するエアサスとも異なるのは、液体の力も利用していること。
ハイドロの略称でも知られるこの方式のサスペンションには、金属製スプリングでは得られない乗り心地の良さや、車高調整が簡単に行えるなどのメリットがあり、特に乗り心地に関しては「雲の上に乗っている」と表現されるほどの極上感があったという。これはオイル量を変化させて車高を一定に保つ能力があったから。
このハイドロサスの開発を積極的に推し進めていたのがフランスのシトロエン。1955年には自社のDSにこのハイドロニューマチック・サスペンションを採用し、その後も改良を続けている。
シトロエン DSのハイドロサスでは、高圧のオイルを使ってサスペンションを支えるが、このオイルはギヤのセレクターやクラッチ、パワーステアリングとブレーキにも活用される総合的なシステムになっていた。ある意味合理的なシステムではあったのだが、どうしても複雑になり、それに起因するトラブルもあった。
スプリングとダンパー(ショックアブソーバー)によるシンプルなサスペンションはトラブルも起こしにくく、コストも抑えることができる。そしてこの伝統的なサスペンションでも、時代が進むに連れて改良が加えられ、乗り心地も改善されていった。
もちろん、シトロエンでも自社のアイデンティティであるハイドロサスを電子化するなどして改良し、最終的にはハイドラクティブIIIプラスと呼ばれるシステムに進化させた。しかし、コストがかかり故障の可能性もそれなりに高かったハイドロサス搭載車は、2017年をもって生産が終了となり、シトロエンもこれ以上の開発・販売を行わないことを公表している。
「雲の上に乗る」「魔法のじゅうたん」などと賛美され、ファンも多かったシトロエンのハイドロサスは、初登場以来60年以上に渡って販売が続けられていたが、エコ重視やEV化などの時代の流れには逆らえなかった。
リトラクタブルヘッドライトはスーパーカーの証?
1970年代中盤に日本国内で巻き起こったスーパーカーブーム。当時の少年たちは、外国製超高性能スポーツカーの先進的なスタイルや高出力のパワーユニットに夢中になった。
そんなスーパーカーのカッコ良さを象徴していたのが、通常走行時はボディ内に収納されていて空気抵抗を抑え、夜間になると立ち上がって照明となるリトラクタブル式ヘッドライトだった。
ポルシェなどの一部のモデルを除いて、スーパーカーブームで人気を集めたクルマの多くにこのリトラクタブルヘッドライトが採用されていて、この人気はやがて超高級車だけでなく、より手の届きやすい国産スポーツカーにも波及していった。
まずはマツダが2ドアスポーツのRX-7でリトラクタブルヘッドライトを採用すると、トヨタもセリカのハイグレードモデル・XXをリトラクタブルヘッドライト仕様にした。そして日産 シルビアやホンダ CRX、そしてトヨタのAE86トレノと、1980年代のスポーティなクルマはこぞってリトラクタブルヘッドライトを装備した。
だが、特に収納時のスマート感は抜群だったリトラクタブルヘッドライトも、機構的に通常のライトより重くなり、コスト高を招くことに加えて、急な故障の際には夜間走行の安全性が低下するなどの問題があったのも事実。
一部の地域ではヘッドライトの最低地上高規制があり、これをクリアするためにリトラクタブルヘッドライトを採用した例もあったが、この規制も緩和され、徐々にリトラクタブルヘッドライトを採用する必然性はなくなっていった。
こうした流れによってリトラクタブルヘッドライトを装備するクルマの数は減少し、現在の新車ラインナップでリトラクタブルヘッドライトの採用例はない。スーパーカーブームを知っている世代にはさみしい限りだが、これもまた時代の必然なのかもしれない。
【画像ギャラリー】あまりに革新的すぎた!? 姿を消してしまったテクノロジー(16枚)画像ギャラリー
投稿 世界を驚愕させたテクノロジーはその後どうなった? は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。