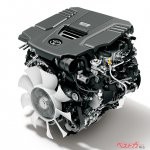東京都は2030年、日本政府は2035年までに純ガソリン車および純ディーゼル車の新車販売を禁止する方針。世界的にも2030~2035年の間に施行されるところがほとんどで、「2050年までにカーボンニュートラル達成」に向けて電動化まっしぐら。
そんななか、マツダが新型3.3リッター直6ディーゼルを開発し、新型CX-60に搭載した。なぜ先細りのように見えるこの時期にディーゼルエンジンを新開発したのか?
まだまだディーゼル車は生き残るのか? ディーゼル車の新車販売はいつまでなのか? いつまでディーゼル車に乗ることができるのか?
文/渡辺陽一郎
写真/ベストカーweb編集部、MAZDA、TOYOTA、MITSUBISHI
【画像ギャラリー】買えるのはあと何年!? 新開発ディーゼルエンジン搭載のマツダ CX-60と各社ディーゼルエンジン搭載車(12枚)画像ギャラリー
■なぜマツダは今、新型直6ディーゼルエンジンを開発したのか?
今はSUVが注目のカテゴリーになり、特にマツダCX-60が高い関心を集めている。
理由はメカニズムに特徴があるからだ。今まで用意されていたマツダ車のエンジンは、直列4気筒で、駆動方式はロードスターを除くと前輪駆動とこれをベースにした4WDだった。ところがCX-60は、後輪駆動のプラットフォームを採用して、直列6気筒エンジンも搭載される。
CX-60のパワーユニットは多岐にわたり、直列4気筒2.5Lガソリン、このエンジンを使ったPHEV(プラグインハイブリッド/充電の可能なハイブリッド)、直列6気筒3.3Lクリーンディーゼルターボ、これをベースにしたマイルドハイブリッドになる。国内仕様では合計4種類をそろえた。
CX-60の国内における登録台数は、1か月に2000台を予定しているが、8月下旬の受注台数は9000台近くに達している。
そして受注台数の内訳を見ると、最も多いのがディーゼルのマイルドハイブリッドで、受注総数の43%を占めた。2位はノーマルタイプのディーゼルで37%、3位はノーマルタイプのガソリンで15%、4位はPHEVで5%になる。
この受注台数の内訳には、受注や生産の開始時期や納期も関係している。販売店は以下のように説明した。
「CX-60では、パワーユニットに応じて、受注や生産の開始時期が異なる。最も早いのはXDハイブリッド(ディーゼルのマイルドハイブリッド)だ。納期は今のところ(2022年10月中旬時点で)約2か月と短い。販売店の試乗も可能だ。
しかしほかのグレードは、受注は行っているが、試乗車は届いていない。納車の開始もPHEVが2023年1月、ノーマルタイプのディーゼルは2月、ノーマルタイプのガソリンは4月以降と遅い」
このようにXDハイブリッドは、販売を早期に開始して納期も短いから、販売比率が43%に達した。逆にノーマルタイプのガソリンエンジンは、納期が最も遅く売れ行きも低迷している。
PHEVは充電と給油を両方ともに行えるから、電気自動車と違って、必ずしも自宅に充電設備を必要としない。しかし販売店では「PHEVを購入するお客様は、ご自宅に充電設備を設置できる一戸建てに住んでいる方が圧倒的に多い」という。
そうなると総世帯数の約40%がマンションなどの集合住宅に住む日本では、電気自動車と同様、PHEVを購入しにくいユーザーが多い。
このような経緯もあり、CX-60では、ディーゼルのXDとXDハイブリッドを合計すると、受注台数の80%を占める。しかもディーゼルは新開発された直列6気筒だから注目度も高い。
燃費性能も優れ、CX-5の直列4気筒2.2LディーゼルとWLTCモード燃費を比べると、CX-60の直列6気筒3.3Lディーゼルは、マイルドハイブリッドでなくてもCX-5よりも優れた数値を達成している。
以上のように直列6気筒ディーゼルは、後輪駆動との相乗効果もあって注目度を一層高め、受注も早期に開始したから売れ行きを伸ばした。
■ディーゼルの二酸化炭素排出量は意外と少ない
今後の動向はどうなのか。CX-60の開発者は「海外ではディーゼルの売れ行きに伸び悩みの傾向も見られ、PHEVは主に欧州市場を視野に入れて設定した」という。
マツダの方針として、2022年から2025年にかけて、ハイブリッドの新型車を5車種、プラグインハイブリッドを5車種、電気自動車を3車種投入するとしている。
この後、2025年から2030年には、複数の電気自動車を導入して、2030年にはすべてのマツダ車に電動技術(エンジンを併用するハイブリッドを含む)を搭載する予定だ。この時の電気自動車の販売比率は25%を想定しているという。
ホンダは2040年までにすべての新車を電気自動車か燃料電池車にする目標を示しており、内燃機関は廃止する計画だ。これに比べるとマツダは、内燃機関とモーター駆動を併用する期間が長いと受け取られる。
直列6気筒3.3Lディーゼルは、新たに設計されたエンジンだから、今後10年以上は使うだろう。つまり2035年頃までは搭載するから、少なくともそれまでに、内燃機関を廃止することは考えにくい。
CX-60に搭載される各パワーユニットの二酸化炭素排出量を売れ筋グレードの4WD仕様で見ると、直列4気筒2.5Lガソリンが167g/km、直列6気筒3.3Lクリーンディーゼルターボは127g/km、ディーゼルのマイルドハイブリッドは123g/km、PHEVは159g/kmとされる。
ディーゼルの二酸化炭素排出量は、ガソリンの76%に収まる。
しかもディーゼルの最大トルクは51kgm、ガソリンは25.5kgmだ。ディーゼルはターボの併用により、ガソリンの2倍に達する最大トルクを発生させて、なおかつ二酸化炭素の排出量は大幅に低減した。
PHEVは充電された電気だけでも走行できるから、再生可能エネルギーによる電気を積極的に使えば、二酸化炭素排出量の発生も大幅に減らせる。それでも給油して走る用途では、ディーゼルは二酸化炭素の排出量を効果的に抑えられる。
最終的には、クルマの動力は電気に置き換わる。欧州には、既にCX-60のPHEVだけを販売している地域もある。従ってマツダの直列6気筒ディーゼルは、乗用車に使われるエンジンとしては最終世代に属するが、動力性能の割に二酸化炭素排出量と燃料消費量が少ない。エンジンの役割を最後まで果たす。
日本の自動車メーカーは、マツダを含めて世界各国でクルマを販売している。開発者は「アフリカのように充電環境の整っていない地域では、今後もエンジンを搭載したクルマのニーズが続く。そこを(充電環境の整っていない地域のユーザーを)見捨てることはできない」と述べている。
■これからディーゼル車の運命は?
ディーゼル車の新車販売については、現時点の規制や法規から考えれば、2035年まで販売できる。
ノルウェーの2025年が一番早く、ドイツ、イギリス、オランダ、スウェーデンが2030年、中国、アメリカ、日本が2035年までに新車販売禁止としている。都市としては東京、ロサンゼルスが2030年、カリフォルニア州、ニューヨーク州が2035年。
ガソリン車、ディーゼル車を通行禁止とする主要都市としては、バルセロナが2020年までに2000年以前に生産された純ガソリン車および2006年以前に生産されたディーゼル車が通行禁止としたほか、パリは2025年までにすべてのディーゼル車の通行禁止としている。
コペンハーゲン、アムステルダム、ロンドン、ミラノ、ロサンゼルスは2030年までにガソリン車およびディーゼル車の中心地へ乗り入れ禁止としている。ここに挙げた都市以外でも中心地への乗り入れ禁止とする多く、今後さらに広がっていくと思われる。
日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを達成する目標を掲げているため、少なくとも2050年までは、ガソリンスタンドでガソリンや軽油が販売されているだろう。
今、新車のディーゼル車を買えばいつまで乗れるのか? 少なくとも27年は乗り続けられる。一方、ディーゼル車の新車販売は前述の通り、東京都の場合はあと7年あまり、それ以外の地域ではあと12年買うことができる。
【画像ギャラリー】買えるのはあと何年!? 新開発ディーゼルエンジン搭載のマツダ CX-60と各社ディーゼルエンジン搭載車(12枚)画像ギャラリー
投稿 ディーゼル車は滅びるしかないのか? あと7年~12年で新車が買えなくなる危機 は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。